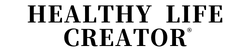新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナウイルス感染症の詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
都内で流行しています
インフルエンザの報告が続いています
インフルエンザの1定点あたりの患者報告数は、荒川区内で第51週2.71人(前週1.2人)、東京都内で第51週2.3人(前週1.12人)でした(1月5日現在)。
都内のインフルエンザ定点医療機関からの第50週の患者報告数が、流行開始の目安となる定点当たり1.0人を超えました。
インフルエンザは例年12月から3月にかけて流行します。3年ぶりの流行シーズン入りとなり、今後本格的なインフルエンザの流行が懸念されるため、注意が必要です。
インフルエンザは、症状が出て7日間はウイルスを排泄し、他の人に感染します。熱が下がっても、人が多く集まる所は避けた方が良いでしょう。学校や職場に行く場合はマスクをし、周囲の人へうつさないように配慮してください。
予防のポイント
予防には、手洗いやうがいを行い、咳エチケットを守りましょう。
インフルエンザの重症化を予防するには、予防接種が有効です。予防接種は受けてから効果が出るまで最低でも2週間以上かかるので、早めの接種をお勧めします。
区内で流行しています
感染性胃腸炎の報告が続いています
特にノロウイルスなどを原因とする感染性胃腸炎の報告が続いています。
感染性胃腸炎の1定点あたりの患者報告数は、荒川区内で第51週26.75人(前週24.25人)、東京都内で第51週10.62人(前週9.56人)でした(1月5日現在)。
11月から2月の時期は集団感染が集中します。
感染経路は、病原体が付着した手で口に触れることによる感染(接触感染)、汚染された食品を食べることによる感染(経口感染)があります。
感染性胃腸炎の流行状況(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ノロウイルスによる胃腸炎の主な症状は吐き気、おう吐、下痢、発熱、腹痛で、小児ではおう吐、成人では下痢が多いです。ロタウイルスによる胃腸炎では、おう吐、下痢、発熱がみられ、乳児ではけいれんを起こすこともあります。
感染しても発症しない場合や、軽い風邪のような症状の場合もあります。
予防のポイント
感染性胃腸炎の予防には、手洗い・二枚貝などの調理における十分な加熱・吐物の適切な処理などを徹底しましょう。また、集団感染の可能性がある施設等においては、施設の衛生的管理など、感染症の予防のため特に注意し対策を行ってください。
部屋やトイレの床に嘔吐しその吐物を処理する場合には、部屋の換気を十分に行いながらマスク・手袋着用のうえ布やペーパータオル等で吐物をふき取り、ふき取ったあとは塩素系消毒剤(0.1%次亜塩素酸ナトリウム)などで消毒してください。
詳しくは社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
感染症情報
感染症ひとくち情報「感染性胃腸炎(ノロウイルス等)にご注意ください」(東京都健康安全研究センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ノロウイルス
ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、24時間から48時間の潜伏期間の後、吐き気・おう吐・腹痛・下痢・発熱(38度以下)などの症状があります。
通常は、発症から3日以内で軽快し、予後は良好です。
感染しても全員が発症するわけではなく、発症しても風邪のような症状ですむ人もいます。
感染性胃腸炎(特にノロウイルス)について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ロタウイルス
ロタウイルスによる感染性胃腸炎が、都内でやや増加しています。24時間から72時間の潜伏期間の後、下痢(3日から8日続き、激しい時には白色で、米のとぎ汁のような便)・おう吐・発熱などの症状があります。
乳幼児では、ノロウイルスによる感染性胃腸炎よりも症状が長引くことが多くあり、合併症として、激しい下痢による脱水症が起こりやすく、時には痙攣・脳炎・脳症など重症化することもあります。大人では無症状の場合も多いといわれています。
平成23年からは、ロタウイルスの予防接種ができるようになりました。
発病や重症化の抑制に効果があるといわれ、生後6週以降32週までに完了することが推奨されています。
感染性胃腸炎(特にロタウイルス)について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
感染症に注意しましょう
麻しん(はしか)
麻しんの患者報告数は、荒川区内で第51週0人(前週0人)・2022年累計0人(2021年累計0人)、東京都内で第51週0人(前週0人)・2022年累計0人(2021年累計0人)でした(1月5日現在)。
麻しんは、例年春から夏にかけて流行すると言われ、典型的には10日から12日間の潜伏期間の後、38℃程度の発熱及びかぜ症状が2日から4日続き、その後39℃以上の高熱とともに発しんが出現します。主な症状は発熱・発しんの他、咳・鼻水・目の充血などです。乳幼児では消化器症状として下痢、腹痛を伴うことが多いことも知られています。症状が出始める1日から2日前から、発しん後4日から5日は、ウイルスを排泄する可能性があります。
しかし、最近では、麻しんの特徴的な症状と経過を示さない症例があることも知られています。また、予防接種を受けたことがある方は、発しん等の典型的な症状がでないこともありますので、症状だけで判断せずに発熱があったら麻しんを疑うことも重要なポイントです。
治療は、対症療法(症状を抑える治療)しかなく、今でも患者さんの1,000人に1人程度が死亡するとされ、合併症で、肺炎、脳炎(1,000人に1人)を起こす可能性があるともいわれ、決して侮れない病気です。
学校保健安全法では、「解熱した後3日を経過するまで」を出席停止の期間としています。但し、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
- 麻しん(はしか)に注意しましょう
- 麻しんの流行状況(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 麻しんQ&A(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 麻しんとは(国立感染症研究所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
予防のポイント
麻しん(はしか)の予防方法は、予防接種が有効です。定期予防接種の対象となる方はぜひ予防接種を受けましょう。定期接種では麻しん・風しんの混合ワクチン(MRワクチン)として接種します。
また、麻しんは感染力が強く、大人の発症も多いため、定期予防接種の対象以外の方も、本人が感染しないためだけではなく、家族などの身近な人へ感染させないためにも、予防接種を検討しましょう。
荒川区では、区内在住で麻しん風しんの定期予防接種を未接種または1回接種の2歳から18歳までの方を対象に予防接種費用の助成を行っています。詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
麻しん風しん予防接種の特別対策について(健康推進課健康推進係)
風しん
風しんの患者報告数は、荒川区内で第51週0人(前週0人)・2022年累計0人(2021年累計0人)、東京都内で第51週1人(前週0人)・2022年累計3人(2021年累計2人)でした(1月5日現在)。
風しんは、発熱・発しん・リンパ節の腫れなどを主症状とするウイルス性の疾患です。「三日はしか」とも呼ばれています。学童期から思春期に多いと言われていますが、最近では成人での発症も多く、職場内での集団感染事例も起こっています。通常2週間から3週間(平均16日から18日)の潜伏期間の後、発熱、淡紅色の発しん、リンパ節の腫れなどが出現します。大人が罹患すると、その症状は小児に比べ一般に重いといわれています。
風しんは妊娠初期にかかると、白内障、先天性心疾患、難聴を主症状とする先天性風しん症候群(CRS)の児が生まれる可能性があり、特に妊婦では予防が必要な、代表的な感染症のひとつです。また妊婦だけでなく、妊婦のパートナーや働き盛りの男性にも注意が必要です。
学校保健安全法では、「発しんが消失するまで」を出席停止期間の基準としています。但し、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
予防のポイント
風しんは予防接種で防げる病気です。定期予防接種の対象となる方はぜひ予防接種を受けましょう。
これから妊娠する可能性のある女性は、妊娠前に予防接種を受けておくことが大切です。
過去に風しんに罹ったかどうか記憶が不確かな場合は、医療機関で抗体価の検査を受け必要に応じ予防接種を受けることをお勧めします。
荒川区で行っている予防接種対策については、下記をご確認ください。
麻しん風しん予防接種の特別対策について(健康推進課健康推進係)
その他の注目すべき疾患
サル痘
サル痘は、サル痘ウイルスによる感染症で、中央アフリカから西アフリカにかけて流行しています。日本では感染症法上の四類感染症に指定されています。
また、2022年5月以降、欧州や米国等で市中感染の拡大が確認されています。日本でも海外渡航歴のある方の患者が確認されました。
- サル痘の潜伏期間は6~13日(最大5~21日)とされており、潜伏期間の後、発熱、頭痛、リンパ節腫脹、筋肉痛などの症状が0~5日続き、発熱1~3日後に発疹が出現、発症から2~4週間で治癒するとされています。
- サル痘の流行地では、げっ歯類やサル・ウサギなどの動物との接触や、感染が疑われる人の飛沫・体液等を避ける、手指衛生を行うなど、感染予防対策を心がけ、感染が疑われる場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
蚊媒介感染症
蚊の発生が多い国に行ったり、蚊に刺される機会が増えると、ジカウイルス感染症(ジカ熱)、デング熱、チクングニア熱といった、蚊が媒介する感染症にかかるリスクが高まります。日本国内では、ウイルスを持ったヒトスジシマカに刺されることで感染し、ヒトからヒトには感染しません。ワクチンはありませんので、蚊に刺されないように予防することが大切です。
潜伏期間は2日から15日で、発熱、頭痛、筋肉痛、発疹などの症状が現れます。症状が出た時は、早めに医療機関に受診しましょう。
詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
鳥インフルエンザ
人から人への持続的な感染は確認されていませんが、中国、香港、台湾に滞在する方は、今後の情報に注意していただくとともに、手洗いや咳エチケットをこころがけてください。また、鳥に直接触ったり、病気の鳥や死んだ鳥に近寄ったりしないようにしましょう。
詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
中東呼吸器症候群(マーズ)
中東呼吸器症候群は、2012年に初めて確認されたウイルス性の感染症で、原因となるウイルスはMERS(マーズ)コロナウイルスと呼ばれています。
どのようにして感染するかは、まだ正確には分かっていませんが、患者から分離されたMERS(マーズ)コロナウイルスと同じウイルスが、中東のヒトコブラクダから分離されていることなどから、ヒトコブラクダがMERS(マーズ)ウイルスの感染源動物の一つであるとされています。
中東地域に渡航する方はラクダなど動物との接触や、殺菌されていない乳や肉の喫食を避けましょう。
中東呼吸器症候群(マーズ)予防ポスター(PDF:289KB)
主な症状は、発熱、せき、息切れなどです。下痢などの消化器症状を伴う場合もあります。中東呼吸器症候群に感染しても、症状が現われない人や、軽症の人もいますが、特に高齢の方や糖尿病、慢性肺疾患、免疫不全などの基礎疾患のある人で重症化する傾向があります。
38℃以上の発熱や咳などの症状があり、過去14日以内に中東地域に渡航歴のある方や韓国において中東呼吸器症候群が疑われる患者の医療・介護に携わった方については、保健所にご相談ください。
詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
- 中東呼吸器症候群(マーズ)について
- 感染症ひとくち情報「中東呼吸器症候群(マーズ)とは」(東京都健康安全研究センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 中東呼吸器症候群(マーズ)に関するQ&A(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 中東に渡航する方へ<中東呼吸器症候群に関する注意>(厚生労働省検疫所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
エボラ出血熱
エボラ出血熱は、主として患者の体液等(血液、分泌物、吐物・排泄物)に触れることにより感染する疾病です。
これまでに、アフリカ中央部のコンゴ民主共和国、スーダン、ウガンダ、ガボンやアフリカ西部のギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ、ナイジェリア、コートジボワールで発生しています。
詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
- エボラ出血熱(東京都感染症情報センター)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- エボラ出血熱について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- エボラ出血熱とは(国立感染症研究所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
感染症の予防は日常の生活習慣から
手洗い・うがい・咳エチケット・バランスの良い食事・十分な休養・体調管理など、感染症予防には日常の生活習慣が大切です。
感染症の患者報告数
荒川区における感染症の患者報告数グラフは、東京都の「感染症週報」をもとに、区内の感染症流行状況がわかりやすいように保健所が作成したグラフです。
感染症の患者報告数グラフの見方
グラフの縦軸は、1定点医療機関あたりの報告数(麻しん、風しんは全数報告)です。東京都に比べると、荒川区内の定点医療機関数が少ないため、値の変動が大きくなっています。
また、グラフの横軸は、週になります。週の始まりは月曜、終わりは日曜となります。第1週は、令和元年12月30日(月曜)から令和2年1月5日(日曜)になります。
定点医療機関
定点医療機関とは、感染症の発生状況を知るために一定の基準に従って1週間当たりの感染症罹患者の数を報告していただく医療機関のことです。
定点には、インフルエンザ定点(小児科定点、内科定点)、小児科定点、眼科定点、性感染症定点、基幹定点の5種類があり、流行状況について全体の傾向ができるだけ反映できるように、医療機関の中から、保健所管内の人口に応じた数の定点医療機関を東京都が指定しています。
荒川区内では、小児科定点医療機関4ヵ所、内科定点医療機関3ヵ所、眼科定点医療機関1ヵ所、性感染症定点医療機関1ヵ所、基幹定点(別名:病院定点)医療機関0ヵ所が東京都から指定されています。
このうち、小児科定点医療機関4ヵ所と内科定点医療機関3ヵ所をあわせた7ヵ所がインフルエンザ定点として指定されています。また区独自で5か所の医療機関から報告を受けています。
定点医療機関は、厚生労働省令で定める感染症の発生状況(患者数)を、週1回荒川区保健所を経由して東京都に届出ることとなっています。
定点医療機関あたりの報告数
1週間にひとつの定点(医療機関)からどのくらいの報告があったかを表す数値です。この数値によって感染症の流行状況が把握できます。保健所管内の当該感染症報告全数を定点医療機関数で割った数値が定点あたりの報告数になります。
例えば、荒川区保健所管内でインフルエンザの報告が24件あった場合、報告数(24件)を定点医療機関の数(荒川区のインフルエンザ定点は都の指定7ヵ所、区独自5ヵ所の計12ヵ所)で割ります。この場合は、24÷12=2.00となり、荒川区内のインフルエンザの流行状況を推計することができます(麻しん、風しんは全数報告です)。
関連情報
お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504